地震・台風・大雨など、災害はいつ起こるかわかりません。
電気や水道、ガスが止まってしまったときに「準備しておけばよかった…」と後悔しないように、日頃から防災グッズを揃えておくことが大切です。
この記事では、停電や断水といった緊急時に役立つ防災グッズ10選を紹介します。
特に「電源の確保」は生活の質に直結するため、ポータブル電源などもおすすめします。
なぜ防災グッズの備えが必要なのか?
近年、自然災害が増加していると言われています。
これに伴い、私たち一人ひとりが備えておくべき防災グッズの重要性はますます高まっていますよね。
特に、都会に住んでいると「自分の生活空間は安全だ」とつい安心しがちですが、現実には予期せぬ事態がいつ起こるか分かりません。
防災グッズを整えることは、単なる備えではなく、自分自身や家族を守るための大切な行動です。
災害リスクがある中で、何も準備していないのはちょっと心配ですよね?
防災グッズを備えておくことで、いざという時の不安がグッと軽減されます。
家族みんなが安心して過ごせる環境を作ることができるんです。
過去の災害が教えてくれること
東日本大震災では、都市部でも大規模停電が発生しました。
物流もストップし、スーパーやコンビニの棚から商品が消えた光景は記憶に新しいですよね。
また、2019年の台風15号では千葉県内で大規模停電が発生し、一部地域では復旧まで2週間以上かかりました。
こうした事例からも分かるように、「電気や水は当たり前にある」という考えは通用しません。
ライフラインが止まったときにどう対応するかが、防災グッズの役割です。
例えば、簡易トイレや水の備蓄、非常食などは、このような緊急時にはとても重宝しますし、普通の生活では考えずに済むことかもしれませんが、これは非常時には自分や家族の命を繋ぐための大事な道具です。
自身が何を持っているか、どのように使うかを知っていることで、心の余裕を持った行動が可能になります。
コストパフォーマンスの良い投資
「防災グッズって高そう…」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、実はとてもコスパの良い投資なんです。
基本的な防災セットなら1万円程度から揃えることができますし、一度購入すれば長期間使えるものがほとんど。
例えば、家族4人分の3日分の備えを揃えても、外食1回分程度の費用で済むことが多いんです。
これで家族全員の安全と安心が得られると考えれば、決して高い買い物ではないですよね?
また、最近の防災グッズは普段使いもできる工夫がされているものが増えています。
ポータブルバッテリーはアウトドアでも活躍しますし、防災用の食品も登山やキャンプで重宝します。
つまり、災害時だけでなく日常生活でも価値を発揮してくれるんです。
防災グッズの備えは、保険と同じような考え方ができるかと思います。
使わないに越したことはないけれど、いざという時の安心料として考えれば、とても合理的な選択と言えるでしょう。
停電・災害に備える!家庭で用意しておきたい防災グッズ10選

ここからは、実際に役立つ防災グッズを10個紹介します。
1. ポータブル電源
災害時に最も頼りになるのが ポータブル電源。スマホの充電はもちろん、小型家電にも電力を供給できます。
停電時に実際どう役立つ?
例えば、真夏に停電した場合。スマホの充電が切れて情報が得られないのはもちろん、扇風機などが使えないのは命に関わります。
冬なら電気毛布やヒーターを動かせるかどうかが快適さを左右します。
そんなとき、メガパワーステーションやパワーバンクキューブネオがあれば小型家電を動かすことができ、家族の安心感につながります。
どちらもコンパクトな軽量設計になってますから、非常時でも持ち出しやすく、アウトドアや車中泊など普段からでも使いやすいというメリットもありますよ。
\メディアで話題になったポータブル電源関連記事/
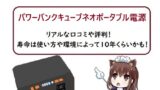


2. LEDランタン
停電時の明かりと言えば、多くの方が懐中電灯を思い浮かべるかもしれません。
でも実際に災害を経験された方の多くが口を揃えて言うのが「ランタンがあって本当に助かった」という言葉なんです。
最近のLEDランタンは本当に進化していて、明るさを細かく調整できたり、暖色と白色を切り替えられたりするものが増えています。
災害時だけでなく、キャンプやアウトドア、そして普段の生活でも活躍してくれる頼もしい存在になってくれるでしょう。
懐中電灯とどう違う?
懐中電灯はスポット的に光を当てるのに適していますが、広い範囲を照らすのには不向きです。
停電時、部屋全体を明るくするならランタンタイプが便利。
吊るしたり、机に置いたりできるので、手が空くのもメリットです。
実際、避難所でも「ランタンを持っている人の周りに人が集まる」ことがよくあります。
懐中電灯だと、何か作業をしようと思っても片手がふさがってしまいますよね?
料理を作るにしても、薬を飲むにしても、本を読むにしても、とにかく不便。
でもランタンなら置くだけで周囲を明るくしてくれるので、両手が自由に使えます。
また、心理的な効果も大きく違うんです。懐中電灯の細い光だと、どうしても不安感が募ってしまいがち。
でもランタンの柔らかい光に包まれていると、不思議と落ち着いた気持ちになれるものです。
3. 携帯・防災ラジオ
現代社会では、情報収集といえばスマートフォンが当たり前になっていますよね。
でも災害時に頼りになるのは、実は昔ながらのラジオなんです。
「え、今どきラジオ?」と思われるかもしれませんが、これが本当に重要な役割を果たしてくれるんですよ。
テレビは停電で見られなくなり、インターネットは回線が混雑して接続できなくなることが多い中、ラジオは比較的安定して放送を続けられるんです。
携帯ラジオは軽量でコンパクト、しかも消費電力が少ないという三拍子揃った優秀なツール。
手のひらサイズのものでも、災害時には家族全員の命を守る大切な情報源になってくれるでしょう。最近では多機能タイプも増えていて、ライト機能やスマホ充電機能が付いたものもあるんです。
スマホだけでは不十分な理由
災害時は通信が混雑し、スマホがつながらなくなることがあります。
東日本大震災のときも「電話が全く通じなかった」という声が多く聞かれました。
その点、ラジオは電波が入りやすく、重要な防災情報を安定的に得られます。特に手回し式やソーラー充電対応のラジオは「電池切れ」の心配を減らせるので安心です。
FM放送なら半径約40~60km、AM放送なら数百kmの範囲に電波が届くので、災害で一部の中継局が被害を受けても、他の地域から電波を受信できる可能性が高いんですね。
さらに、スマートフォンはバッテリーの消耗が激しいという問題も。
動画視聴やアプリ使用で、あっという間に電池が切れてしまいますよね。
でも携帯ラジオなら、単3電池2本で20時間以上連続使用できるものがほとんど。この差は災害時にはとても大きいと思います。
4. 保存水(飲料水)
水は生命維持に欠かせない最重要アイテムです。食べ物がなくても2~3週間は生きられますが、水がないと2~4日で命に関わってきます。
だからこそ、防災グッズの中でも特に優先して備えておきたいのが保存水なんですね。
人が1日に必要な水は約3リットル。最低でも3日分、できれば1週間分の備蓄が望ましいです。
ペットボトルの水をローリングストックすると負担なく備えられます。
必要な水の量を具体的に計算してみよう
まずは、ご家族に必要な水の量を具体的に計算してみましょう。これを把握しておけば、どれくらい備蓄すればいいか明確になります。
4人家族の場合を例にしてみますね。
1人1日3リットル×4人×7日分=84リットル。2リットルのペットボトルで考えると42本も必要になります。
「こんなに?」と驚かれるかもしれませんが、実際にこれだけあると本当に安心できるんです。
ただし、この84リットルというのはあくまで飲料水と調理用水の話。手を洗ったり、食器を洗ったり、トイレで使ったりする生活用水を含めるとさらに多くの水が必要になるんですね。
これを全て備蓄するのは現実的ではないので、飲料水は備蓄、生活用水は給水車や井戸水を活用するという考え方が基本になります。
子供や高齢者がいるご家庭では、少し多めに計算しておくと安心です。
特に乳幼児のミルク作りには清潔な水が必須ですし、薬を飲む必要がある高齢者の方にも十分な水を確保してあげたいですよね。
ペットを飼っている方は、ペットの分も忘れずに。
犬や猫も1日に体重1kgあたり50~100mlの水が必要ですから、中型犬なら1日約1.5リットルは必要になる計算です。
\保存水はいろいろなショップでありますよ/
5. 非常食
災害時に何より重要なのは、やはり食べ物の確保です。電気やガスが止まっても、お腹が空いては体力も気力も続きませんからね。
でも、ただ食べ物があればいいというものでもないんです。
アルファ米や缶詰、ビスケットなど「温めなくても食べられるもの」を選びましょう。最近は美味しい防災食も増えています。
非常食選びの基本原則
非常食を選ぶ時には、いくつかの重要なポイントがあります。こ
れらを押さえておけば、いざという時に本当に役立つ食べ物を備蓄できるはず。
まず最も大切なのが「火や電気を使わずに食べられること」。
災害時は電気もガスも止まっている可能性が高いですからね。水だけで戻せるもの、そのまま食べられるものを中心に選ぶのが基本です。
「保存期間の長さ」も重要な要素。
最低でも3年、できれば5年以上保存できるものを選んでおくと管理が楽になります。
ただし、保存期間だけを重視して味を犠牲にするのはおすすめしません。災害時でも美味しく食べられることは、心の健康にも大きく影響するんです。
「栄養バランス」も考慮したいポイント。
炭水化物だけでなく、タンパク質やビタミン、ミネラルも摂取できるよう、バランスよく備蓄しましょう。特にビタミンCは不足しがちなので、野菜ジュースや果物の缶詰なども一緒に備えておくといいですね。
「家族の好み」に合わせることも大切。
いくら栄養価が高くても、家族が食べたがらないものでは意味がありません。普段から家族で試食してみて、みんなが納得できるものを選ぶことをおすすめします。
「調理の簡便さ」も忘れてはいけません。
災害時は心身ともに疲労している状態。複雑な調理が必要なものよりも、開けるだけ、お湯を注ぐだけで食べられるものの方が実用的です。
主食系の非常食
お米やパンなどの主食は、エネルギー源として欠かせません。
災害時でも「ちゃんとした食事をしている」という満足感を得るためにも重要な役割を果たしてくれます。
「アルファ米」は非常食の定番中の定番。
味も昔と比べて格段に向上していて、普通のご飯とそれほど変わらない美味しさなんです。
「パンの缶詰」も人気が高まっています。
缶を開けるだけでふわふわのパンが食べられて、チョコレート味やイチゴ味など、子供が喜びそうなフレーバーもたくさん。朝食やおやつ代わりにも重宝するでしょう。
また、非常食の備蓄は、日常生活でも役立ちます。
忙しいときや体調が優れないときに、すぐに食べられるものがあるとあんしんです。
家族や友人を招いてのアウトドアやキャンプの際にも、手軽に持ち運べる非常食を用意しておくと、安心ですよ。
このように、非常食は単なる備蓄品ではなく、日常生活においても役立つアイテムになります。
ぜひ、各家庭でお気に入りの非常食を用意して、不安を軽減するための備えをしておきましょう。
6. モバイルバッテリー
現代の災害対策で絶対に欠かせないのが、スマートフォンの電源確保です。
連絡手段、情報収集、ライト機能など、スマホは災害時に命綱となる多機能ツールですからね。
でも、どんなに高性能なスマホも電池が切れてしまえばただの文鎮と同じです。
普段から持ち歩ける小型の充電器も必須。ポータブル電源と合わせて準備すると安心感が増します。
最近のモバイルバッテリーは本当に進化していて、手のひらサイズでスマホを3~4回フル充電できるものも当たり前になりました。
災害時だけでなく、普段の外出時にも重宝するので、まさに一石二鳥のアイテムと言えるでしょう。
モバイルバッテリーの容量選びのポイント
モバイルバッテリーを選ぶ時に最も重要なのが容量です。
mAh(ミリアンペアアワー)という単位で表示されていますが、この数字が大きいほど多くの電力を蓄えることができます。
特に、ポータブル電源と一緒に準備しておくことで、より安心感が増します。
ポータブル電源は、大容量のバッテリーを積んでいるため、複数のデバイスを同時に充電できるのが大きなメリットです。
災害時には家族のスマートフォンやタブレット、場合によってはLEDランタンなども充電できます。
たとえば、避難所にいるとき、自分の機器が充電できることで、周囲の人々と連絡を取りやすくなります。
それによって、情報も共有しやすくなるんですよ。そういった時に、モバイルバッテリーがしっかりと役割を果たしてくれるのです。
「10000mAh」クラスが災害用としては最もバランスが良いかと思います。
iPhone14なら約2.5回、Android系のスマホなら約2~3回フル充電できる計算。重さも200~300g程度なので、持ち運びも苦になりません。
7. 携帯トイレ
防災グッズの話をする時、なかなか話題に上がりにくいのがトイレの問題ですが、実際のところ、災害時に最も深刻な問題の一つがこのトイレなんですよね。
どんなときでもトイレは待ったなし。人間の生理現象ですから、どうしようもありません。
携帯トイレは、そんな切実な問題を解決してくれる頼もしいアイテム。
コンパクトで軽量、しかも使い方も簡単なので、防災グッズの中でも特に準備しておきたいものの一つです。
最近の携帯トイレは本当に進化していて、臭いを抑える機能や処理のしやすさなど、使う人のことを考えた工夫がたくさん施されているんです。
「凝固剤タイプ」は最も一般的な携帯トイレ。
袋の中に入っている凝固剤が水分を吸収してゲル状に固めてくれます。臭いを抑える成分も含まれているので、処理までの時間があっても比較的安心。
価格もお手頃で、大量に備蓄しやすいのがメリットですね。
8. 防寒グッズ
冬の災害時、特に厳しいのが停電中の寒さです。
普段はエアコンやストーブに頼っているかと思いますが、もしそれらが使えないとなったとき、どれほど過酷な状況になるかを考えると恐ろしいですよね。
そんな時に役立つのが「防寒グッズ」です。
防寒グッズの重要性
アルミブランケット(エマージェンシーブランケット)は、防災グッズの中でも特にコストパフォーマンスに優れたアイテム。
手のひらサイズに折りたためるのに、広げると大人一人がすっぽり包まれるサイズになります。
風がある場所では「風よけ」としても活用できますし、テントのように張ることで、体感温度を大幅に改善できるでしょう。
ただし、アルミブランケットは薄い素材なので、鋭利なものに触れると破れやすいのが難点。取り扱いには注意が必要です。
寝る時に使う場合は、寝袋の中に入れて使うとより効果的。寝袋だけでは足りない寒さの時に、強力なサポート役として活躍してくれるはずです。
寝袋は少し前にメディアでも紹介されてた「SONAENOクッション型着られる寝袋」はいろいろなシーンで使いやすそうでしたよ。
9. 救急セット
災害時には、普段では考えられないような怪我をしてしまうことがあります。
割れたガラスで手を切ったり、避難中に転んで擦り傷を作ったり、慣れない作業で指を挟んだり。そんな時に頼りになるのが救急セットなんです。
絆創膏・消毒液・包帯・ハサミなどをまとめておきましょう。持病の薬や常備薬も忘れずに。
救急セットの内容と必要性
は何を入れたら良いのでしょうか?まず基本的なアイテムとして、絆創膏は必須です。
小さなけがにすぐ対応できるため、特にお子さんがいる家庭では重宝します。
また、消毒液は傷口の感染を防ぐための大切なアイテムです。避難所でも手軽に使えるため、常にストックしておくと安心ですね。
包帯やガーゼも重要なアイテムです。
大きな怪我をした場合には、きちんと止血しなければ危険です。
そのため、「包帯は何枚持っておけばいいかな」と考えるよりも、必要以上に用意しておくのが賢明です。
持病の薬や常備薬については、個々の健康状態に応じて準備する必要があります。
10. 現金(小銭含む)
現代社会では電子マネーやクレジットカードが主流になっていて、「現金なんてほとんど使わない」という方も多いでしょう。
でも災害時には、この現金が思わぬ力を発揮してくれるんです。
停電で電子決済が使えなくなるケースもあります。自販機や公衆電話で使えるよう小銭も用意しておくと安心です。
防災グッズを揃えるときのポイント
防災グッズを準備しようと思っても、「何から始めればいいの?」「どこまで揃えれば安心?」と迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。
確かに、一度に全てを完璧に揃えようとすると、費用も労力も相当なものになってしまいます。
でも安心してください。防災グッズの準備は、一気にやる必要はないんです。
むしろ段階的に、計画的に進めていく方が、実用的で持続可能な備えができるでしょう。
重要なのは「完璧を目指さず、まず始めること」。そして「家族の生活スタイルに合った方法で続けること」なんです。
最近では防災意識の高まりから、様々な防災グッズが市販されています。
でも、パッケージされた防災セットをそのまま買うだけでは、本当に自分の家庭に必要なものが含まれていない可能性も。
自分たちの生活を振り返りながら、必要なものを一つずつ選んでいく過程こそが、真の防災対策につながるのかもしれませんね。
ローリングストックで無理なく備える
まずお勧めしたい方法が、ローリングストック法です。
この方法では、非常食や水を「普段使いしながら買い足す」ことで、無理なく備蓄ができます。
例えば、毎週の買い物で1本の水を積極的に消費し、その分を新たに購入する。こうすることで、常に新しい商品を手元に用意でき、賞味期限が切れてしまう心配も少なくなります。
ローリングストックのコツは「普段食べ慣れているもの」を中心に選ぶこと。
災害時に初めて食べる非常食よりも、普段から親しんでいる味の方が精神的にも安心できます。
レトルトカレー、パスタソース、インスタント麺、缶詰など、家族が好きで普段からよく食べるものを多めにストックしておけば、それが立派な非常食になるんです。
家族構成に合わせて選ぶ
小さい子供や高齢者がいる家庭では、必要な防災グッズが変わります。
例えば乳児がいればミルクやオムツも忘れずに準備しましょう。
赤ちゃんがいるご家庭では、通常の防災グッズに加えて考えることがたくさんありますよね。
粉ミルクは1週間分、オムツは普段の1.5倍程度の量を備蓄しておくと安心。哺乳瓶の消毒用品や、ミルクを作るための水も必要です。
離乳食期の赤ちゃんなら、月齢に応じた離乳食の備蓄も大切。
市販の瓶詰めやパウチタイプの離乳食は、温めなくても食べられるものが多いので災害時には重宝しますし、食べ慣れた味のものを選んで、普段から時々使ってみることをおすすめします。
高齢者がいる場合は、薬の管理が特に重要になってきます。
お薬手帳のコピーを防災バッグに入れておいたり、常用薬は1週間分程度多めに確保したりといった準備が必要。
また、入れ歯の方は入れ歯洗浄剤、杖を使っている方は予備の杖なども考慮に入れてください。
ペットを飼っているご家庭も、ペット用の防災対策が必要ですね。
ペットフードや水、リード、ケージ、トイレ用品、薬などを準備しておきましょう。
避難所にはペットと一緒に入れない場合も多いので、車中泊用の準備やペット同伴可能な避難場所の確認も重要です。
防災グッズに関するよくあるQ&A
防災グッズに関するよくある疑問をQ&A方式でまとめながら解説していきますね。
Q1. ポータブル電源はどれくらい持ちますか?
A. 機種によりますが、スマホなら数回~十数回の充電が可能です。メガパワーステーションのように大容量タイプなら、ノートPCや小型家電の利用もできます。
Q2. ソーラーパネルは実用的?
A. 天候に左右されますが、晴天時であれば十分に充電可能です。停電が長引くときには特に役立ちます。
Q3. 防災グッズはどこに保管すればいい?
A. 玄関近くや寝室など、すぐに持ち出せる場所がおすすめです。複数箇所に分散して保管するとより安心です。
Q4. どれくらいの量を備蓄すればいい?
A. 最低3日分、できれば1週間分の備蓄が推奨されています。家庭の人数に合わせて計算して準備しましょう。
Q5. 子供がいる家庭では何を優先すべき?
A. おむつ・粉ミルク・おしりふきは必須です。避難所では入手が難しいため、家庭で備蓄しておくことを強くおすすめします。
Q6. 防災グッズはどこで買うのがいい?
A. ホームセンターやアウトドアショップ、防災専門店、ECサイトなどで購入できます。ネット通販ではレビューも参考になるので選びやすいです。
Q7. 防災リュックと自宅用備蓄は別に必要?
A. はい。リュックは「すぐに持ち出せる用」、自宅備蓄は「自宅避難用」と役割が異なります。両方を準備しておくのが理想です。
まとめ
防災グッズは「揃えておけば安心」ではなく、「普段から備えて使えるもの」がベストです。
特に 電源の確保 は命に直結する要素。スマホの充電が切れただけで、情報が途絶えてしまいます。
その点、
・パワーバンクキューブネオ
・メガパワーステーション
この2つのポータブル電源はよく通販番組で紹介されてるから口コミも多く参考にしやすいですし、停電への備えはぐっと現実的になります。
そして「水」「食料」「情報」を確保することで、災害時でも最低限の生活を維持できるのです。
この記事で紹介した防災グッズを少しずつ揃えていけば、いざという時に慌てず行動できるはずです。

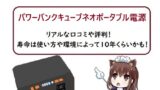
最後までご覧いただきありがとうございます。











